シンポジウムテーマ:スポーツ諸科学とスポーツ教育学の協奏(人文・社会科学系)
スポーツ教育学は「教育学」を基盤として推進されているが、スポーツ諸科学から学ぶべきことは多く、協働すべきであろう。しかしながら本学会の構成員の多くは教育関係者であり、他のスポーツ諸科学との協働はやや薄いと言わざるを得ない。異なる学問領域から、スポーツ教育学はどのように見え、何を期待されているのか、そこで諸科学はどう活用されるべきなのか。また、スポーツ教育学は、スポーツ諸科学にどのように貢献できるのか。ここでは、「協奏」という表現をあえて用い、それぞれのスポーツ諸科学とスポーツ教育学が連携し合い、教育活動をともに推進する方策を検討したい。
シンポジストとテーマ・抄録
「スポーツ哲学とスポーツ教育学」:田中 愛(東京学芸大学)
スポーツとは何か。この問いは,スポーツが本当に教育に役立つのかを再検討するために必要な問いだと言える。
スポーツが疑う余地もないほど善きものであることは,至る所で謳われている。しかし同時に,スポーツ界ではドーピングや暴力の防止が喫緊の課題として叫ばれている。疑う余地もないほど善き活動として推進しつつ,その活動から生じる問題の防止に奔走しなければならないという矛盾は,スポーツがまったく異なる2つ側面を抱えていることを示している。
それでは,この2つの側面は具体的にどのような側面であり,両者はどのように関係し合っているのか。たとえば両者は「善/悪」の二項に対立し,それゆえ「悪」の側面を切り離せば済むことであるのか。またその切り離しは可能であるのか。本報告では,スポーツ哲学・倫理学の知見を借り,具体例を用いた検討を行い,改めてスポーツそのものと教育との接点を考える。

(東京学芸大学)
「スポーツ経営学とスポーツ教育学」 :朝倉 雅史(筑波大学)
日本におけるスポーツ経営学の展開は、戦後、体育施設の管理をはじめとする実学として、「体育管理学」が教員養成に組み込まれたことを端緒としている。その後、運動やスポーツを行う場と機会が学校外で増大していく中、施設(モノ)のみならず人材(ヒト)・財務(カネ)・情報といった「資源」の確保・配分・展開が複雑化し、それらをやりくりする組織や機関も、教員や学校から多様な営利・非営利セクターに広がった。この「スポーツ事業の拡大」は、スポーツ経営に関する研究の蓄積に多大な影響を及ぼしてきたが、それは「スポーツ教育の場や機会」が学校内外に拡張されてきた軌跡でもある。だとすれば今、スポーツ経営学の目的・対象・方法の視点から、スポーツ教育の経営はいかに捉えられるのだろうか。本発表では、スポーツ経営の概念を踏まえながら、学校内外のスポーツ教育に関わる事象を経営学的観点から検討することの意義と課題を考えてみたい。
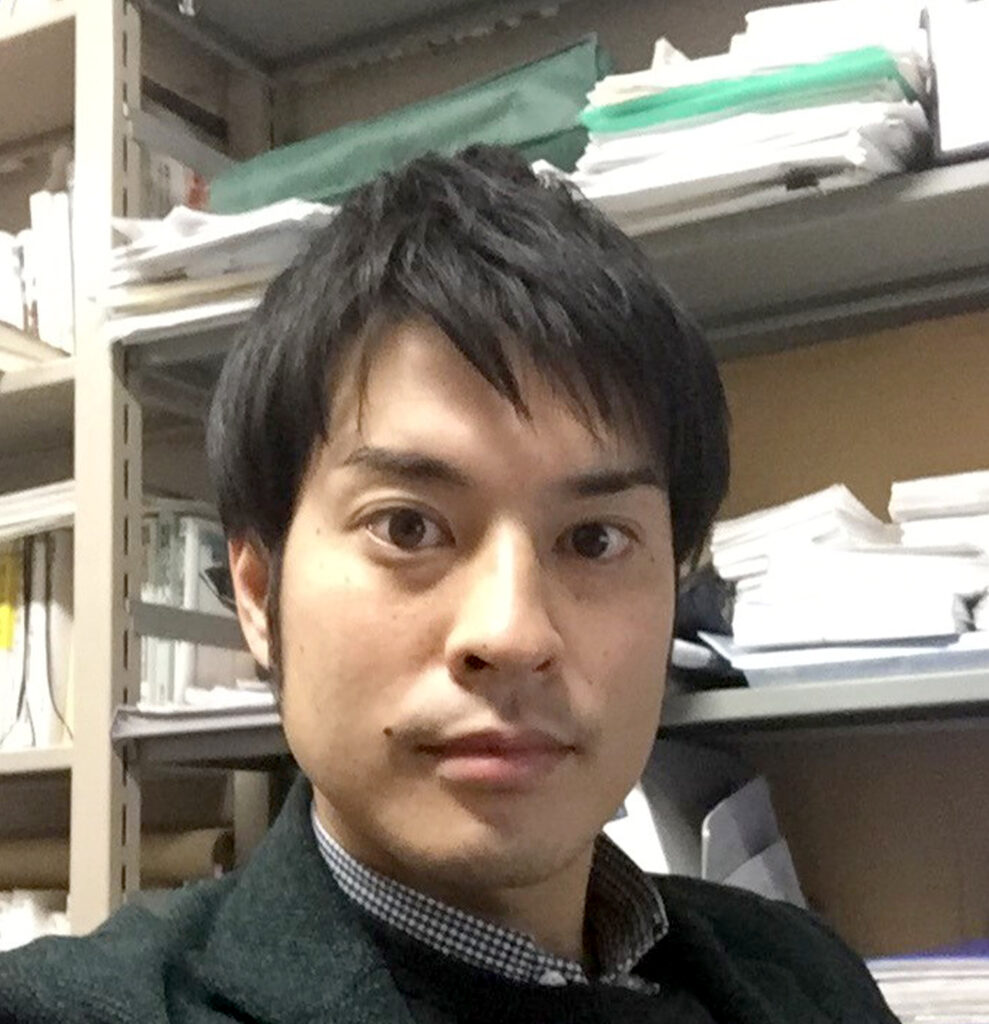
朝倉 雅史
(筑波大学)
「スポーツ心理学とスポーツ教育学」 :豐田 隼(東京大学・日本学術振興会)
アスリートや児童生徒の「こころ」の働きと仕組みを扱うスポーツ心理学は,個人のパフォーマンス発揮の過程からスポーツ・教育界が抱える喫緊の社会課題まで,幅広い現象に関心を寄せる応用心理学の一分野である。他方,今日では改正スポーツ基本法が成立し,スポーツによるwell-beingの向上が強調されたと同時に,指導者による暴力への対策強化やアスリートの人権保護など,スポーツのダークサイドにも明示的に焦点が当てられた。こうしたダークサイドに潜む被害者の心理症状や指導者の信念形成といった「こころ」を巡る現象は,スポーツ心理学が積極的に記述してきた領域である。スポーツの教育的価値が改めて問われている今日,本話題提供では,アスリートセンタードの視点を再考しながら,特に指導者による暴力問題への心理学的アプローチを概観することで,心理社会的な安全性が担保されたスポーツ指導のあり方について,スポーツ教育学との理論的・実践的な接合点を模索する。

豐田 隼
(東京大学・日本学術振興会)
役割分担
- 全体司会 :佐藤善人(椙山女学園大学)
- 指定討論者:佐藤豊(桐蔭横浜大学)・深見英一郎(早稲田大学)
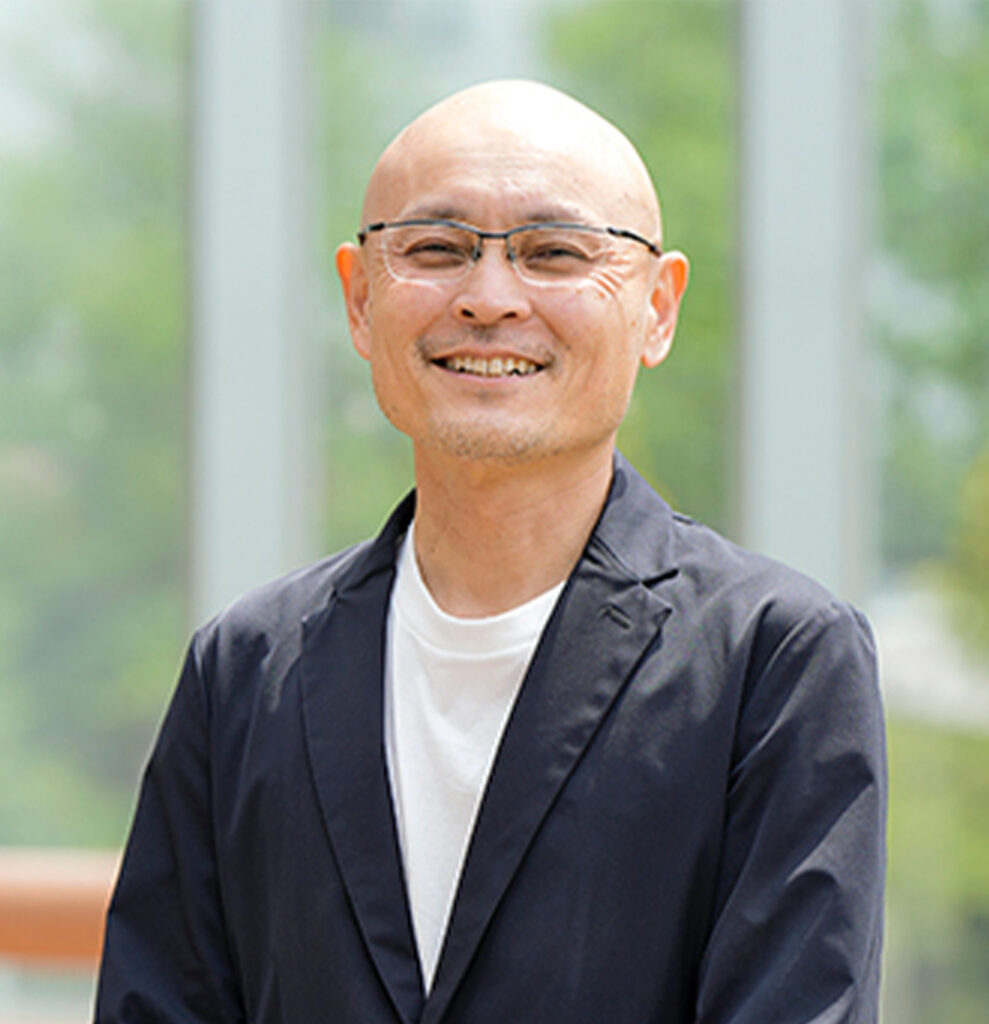
(椙山女学園大学)

(桐蔭横浜大学)

(早稲田大学)
